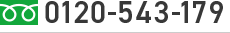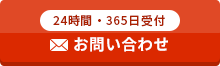| 亡くなられた方 | 母 |
|---|---|
| 相続人 | 長女,二女,三女 |
| 財産(遺産) | 土地,建物,預貯金 |
ご依頼の背景
ご依頼者の母親(被相続人)が亡くなりました。被相続人は亡くなるまで,被相続人の長女と同居していました。
被相続人の次女(ご依頼者)と三女は,被相続人の預金の残高が少ないことを不審に思いました。そのことを長女である姉に言いましたが,取り合ってもらえませんでした。
そのため,ご依頼者は公平な遺産分割を行うために,当職へ相談に来所されました。
依頼人の主張
被相続人は生前,頻繁にご依頼者と連絡を取っていました。被相続人から聞いていた話ではもっと預金(遺産)があっても良いはずでした。
ところが,被相続人の預金は必要以上に減っていたのです。ご依頼者としては,被相続人の長女は被相続人と同居していたため,被相続人の預金を引き出すことは簡単であり,不正な引き出しをしているのではないかという考えでした。
サポートの流れ
当職は,ご依頼者に被相続人の預金の取引履歴を取得してもらいました。
すると,被相続人の死後に合計500万円の預金が引き出されていることが判明しました。
当職は被相続人の長女を相手方として,遺産分割調停の申立てを行いました。調停手続において,長女は500万円を出金したこと自体は認めました。
しかし,その引出しは被相続人のために支出した費用であると主張しました。500万円のうち100万円については使途などの詳細な資料を提出してきました。
そのため,ご依頼者は100万円の出金については納得することが出来ました。
しかし,残りの400万円については納得できませんでした。
相続法の改正により,相続人の一人が預貯金を引き出した場合,その相続人の同意がなくても,引き出された預貯金を遺産分割の対象とすることが出来るようになりました(民法第906条の2)。
そのため,残りの400万円の使途不明金については,引き出しをした長女の同意なく,二女及び三女が同意すれば,遺産分割の対象にできる(遺産として存在するものとみなすことができる)ようになりました。
当職は民法第906条の2に基づき,400万円が遺産分割の対象になることを主張しました。
結果
裁判所によって当職の主張は認められ,残りの400万円についても遺産分割の対象とすることが出来ました。
本来であれば,引き出しをした長女の同意が無い限り,不当利得返還請求訴訟や不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を起こさなければ,引き出された400万円については解決できないはずでしたが,すんなり解決することが出来ました。
ご依頼者は裁判をすることなく,公平な遺産分割をすることができ,喜んでいました。
その他の解決事例
| 亡くなられた方 | 父親 |
|---|---|
| 相続人 | 長男,長女,次女 |
| 財産(遺産) | 土地,預貯金 |
その他の解決事例
| 亡くなられた方 | 母 |
|---|---|
| 相続人 | 長男,長女 |
| 財産(遺産) | 土地,建物,預貯金 |
その他の解決事例
| 亡くなられた方 | 父親 |
|---|---|
| 相続人 | 長男,長女,次女 |
| 財産(遺産) | 土地,建物 |